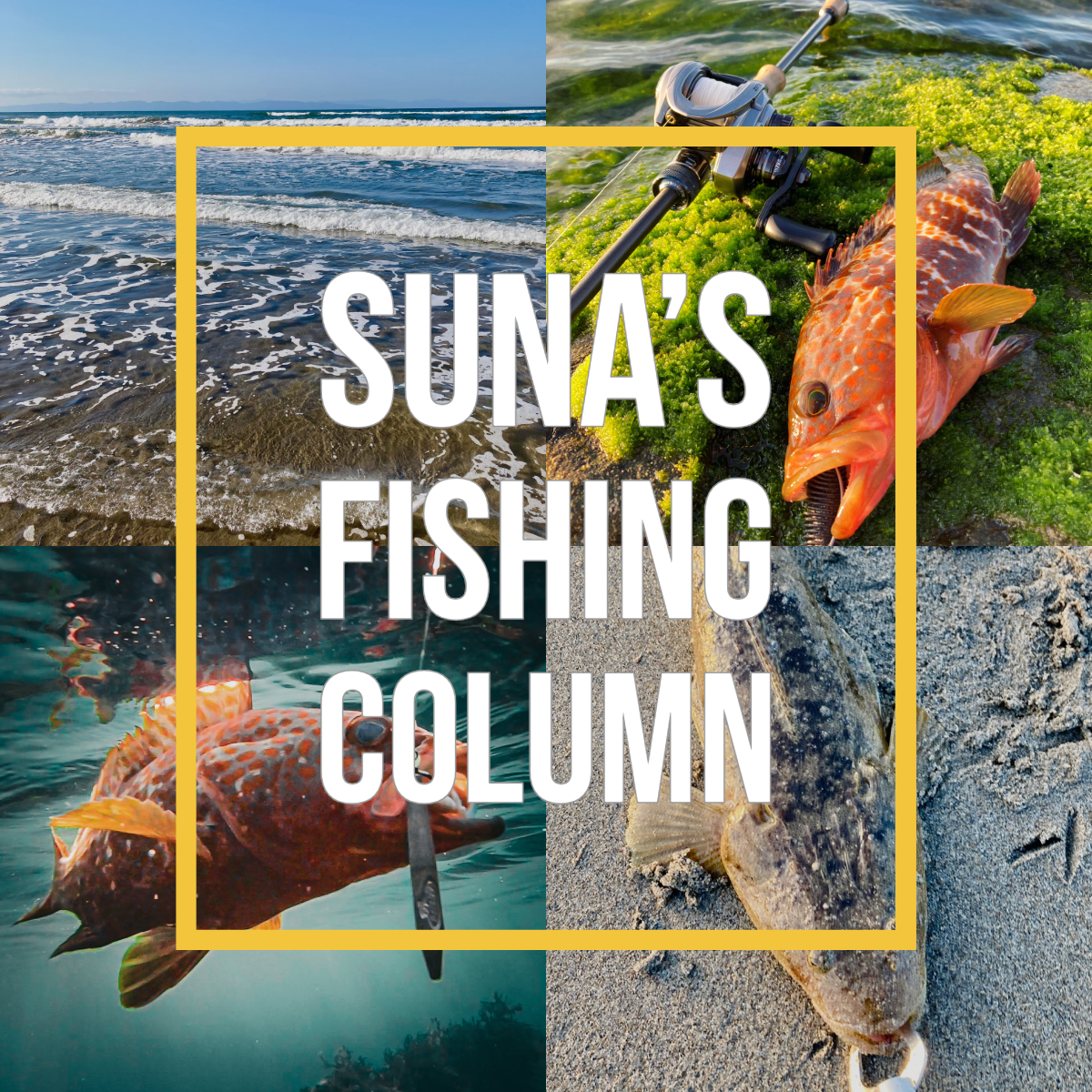マジメな?コラムのコーナーです。ご興味のある方はお時間のある時にどうぞ。
バスの色覚にまつわるサイエンス
バークレイの伝説的な人物であるキース・ジョーンズ博士が「Knowing Bass: The Scientific Approach to Catching More Fish」を出版したのは2002年のこと。ブラックバスにまつわる科学的な見地が詰まったこの書籍は、釣り人の経験則に基づく言説の多かった時代に大きなインパクトを伴って迎えられました。
実のところ、アメリカでは古くからバスに対する科学的アプローチが盛んであり、「Knowing Bass」が世に出る前から多くのことが解明されていました。一例を挙げれば、ブラウン・フランク・Jr. が「Responses of the Large-mouth Black Bass to Colors」を報告したのは1937年です。これはバスの色覚を解き明かした初期の科学研究のひとつとして知られています。しかし、それさえもドイツのシュヌールマンが1920年に報告した内容に触れていますから、連綿と続く科学研究を辿ろうとすれば国と言語を跨ぎながら100年遡ったとしても到底語り尽くせません。
それは楽しい作業であると同時に大変な作業でもあるので、今回は比較的に新しい報告に目を向けたいと思います。2018年から2019年にかけてリサ・ミッチェムが報告した「Seeing red: color vision in the largemouth bass」は現代の文章なので(学術論文の中では)読みやすいほうです。この中でバスが赤色を正確に区別できるという事実はブラウン・フランク・Jr. が報告していた内容と一致しています。80年の時を超えてバスの色覚が同じであると確かめられたことは釣り人にとっても興味深い内容だと思います。これはつまり、私たちがどんな色のルアーを投げ続けたところで、根本的にはバスの色覚は変わらないということです。
バスは目が悪い?
さて、ブラウン・フランク・Jr. もリサ・ミッチェムも、ブラックバスは2色型色覚であると報告しています。このことはバスの釣り人にとっては常識となっているかもしれません。しかしながら、ヒトよりも色覚が少ないという点を誤解して「バスは目が悪い」と勘違いしている言説を見かけることもあります。
ここでデータを見てみましょう。下表はバスの目の中にあるカラーセンサーである各錐体細胞の最大視感度を一覧にしています。参考としてヒトのデータも並べました。
| 和名 | Blue | Green | Red |
|---|---|---|---|
| オオクチバス | N/A | 535 nm | 614 nm |
| ヒト | 420 nm | 527 nm | 557 nm |
確かにバスには青色に対応する錐体がないようですが、これを理由にヒトより劣ると考えるのは早計です。汽水や淡水などの環境は有機物が多いので濁っています。そのような環境では短い波長である青色光は散乱してしまい水中深くに届かなくなります。そのため長い波長である赤色光を頼りにしたほうが水中での視界を得ることができます。
いずれの錐体細胞でもバスはヒトよりも長い波長に対応しています。つまり、河川や湖沼においてはヒトよりもバスのほうが目が良いと考えられます。しかも、不要なセンサー(青錐体)を廃している分だけ網膜上のスペースを有効利用できているはずですから、上表の数値から受ける印象以上に感度と解像度の両面で優れているのかもしれません。
バスは本当に2色型色覚なのか?
さて、バスは2色型色覚であることが確かめられています。ところが、ゲノム研究からは不思議な報告もあります。バスは青錐体を作るSWS2というゲノムを持っていることが知られているからです。下表は錐体細胞に関わるゲノムの一覧です。こちらも参考としてヒトのデータも載せています。
| Species | 和名 | SWS1 UV | SWS2 Blue | RH2 Green | LWS Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Micropterus salmoides | オオクチバス | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Homo sapiens | ヒト | 1 * | 0 | 0 | 3 ** |
** ヒトは LWS をGreenとRedの2種類に分化して利用している。個数は個人差があり、中央値は3。
このデータからはバスが3色型色覚であるように思います。一体どういうことなのでしょう?
小難しい説明は割愛して、簡単な例え話をします。
皆さんは学校の授業で木工を習ったと思います。私の場合は小さな本棚を作ることが課題でした。始めに先生が基本の設計図を示しましたが、私が作った本棚はそれとは少し異なる結果になりました。ここでいう設計図にあたるものがゲノムであり、結果が表現型と呼ばれるものです。
要するに、あるゲノムがあったからといって、実際の生物がそれを発現させているとは限らないということです。事実、ヒトのデータは私たちが設計図にアレンジを加えて表現型を作っていることを示しています。上表はかなり単純化しており、本当はもっと複雑です。
バスは3色型色覚のゲノムを持っていた。表現型を調べたら2色型色覚だった。この2つの事実は矛盾しないのです。
3色型色覚のバスを探す
それでは、3色型色覚のバスは実質的には存在しないのでしょうか?
ジェイソン・ヒルが2019年に報告した「Recurrent convergent evolution at amino acid residue 261 in fish rhodopsin」はニシンの桿体細胞(暗所で働く細胞)とゲノムに関する研究です。この中に興味深い仮説が登場します。
この研究の本筋では大西洋のニシンとバルト海のニシンを比較することで、バルト海のニシンが赤色光優位環境に適応した視覚システムを持っていることを明らかにしています。ところがその過程でバルト海のニシンの中でも春生まれと秋生まれの間で違いが見つかったというのです。
この点についてジェイソン・ヒルは稚魚期における環境の違いに着目しています。サケは大半の時期を海で過ごしますが、稚魚期を過ごす淡水環境に適応した視覚システムを持ちます。また、ウナギは海で生まれるので海水環境に適応した視覚システムを持ちますが、成魚は淡水で暮らしています。おそらくはバルト海のニシンも稚魚期における季節的な環境変動に合わせて異なる視覚システムを持って生まれるのではないかと述べられています。
もしかするとバスも青色光優位環境では異なる視覚システムを持ち、3色型色覚を持つ個体もいるのかもしれません。水質がクリアで、水深もそれなりにある環境が該当しますが.. なかなかそのような湖は少ないような気がします。
海水に棲む魚の大半はSWS1とSWS2を持っており、それによって水中のプランクトンを容易に見つけることができます。しかし、バスにはSWS2しかないので用途が異なると考えられます。バスのSWS2が何のために存在しているのかがわかれば、3色型色覚のバスを見つけることもできるかもしれませんね。
今回のコラムはここまで。魚の色覚とルアーカラーについては興味が尽きません。他にもコラムを書きますので引き続きチェックしていただければと思います。